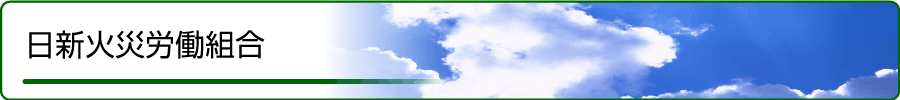日新労組
ニッシンロウソ
|
日新火災(本体)にある労働組合。日新労組では労働協約(会社と組合との間で労働条件その他についての取り決めを書面にあらわしたもの、Vネットにも掲載あり)において、管理職や一部の人を除いて社員は全員が日新労組に加入している(これをユニオンショップ制という)。組合員ではない管理職の人を非組(ヒクミ)と呼ぶこともある。 |
分会
ブンカイ
|
会社の機構にあわせ、原則として本支店ごとに置くこととしており、現在全国で12の分会がある(札幌、仙台、東京、さいたま、横浜、静岡、名古屋、金沢、大阪、広島、高松、福岡)。日新労組の組合員であれば必ずいずれかの分会に属することになっている。分会は本部と職場の間で、本部が定めた方針を職場に徹底したり職場の意見をとりまとめて本部に報告することや、部支店経営と交渉・協議を行なうなどの役割を担っている。なお、高松分会は本部の運営事務局が実際の運営を行なっている。 |
組合大会
クミアイタイカイ
|
日新労組における最高議決機関。定例的に開催される9月、3月の組合大会に加え臨時に開催されることもある。組合大会に参加するのは本部の執行委員と各分会から選出された代議員である。組合大会では、年間の組合の運動方針(9月)や春闘で要求する方針(3月)などについて審議、決定している。また9月の大会で期が入れ替わり、本部役員(執行委員)の選挙も行われている。 |
分会総会、
分会大会
ブンカイソウカイ、
ブンカイタイカイ
|
分会における最高議決機関。分会によって組合員全員が参加する分会総会と職場の代議員のみが出席する分会大会とに分かれる。通常は組合大会の前の9月、3月に開催され、分会での審議の他、組合大会への代議員も選出している。また、分会役員選挙も行なわれている。 |
本部オルグ
ホンブオルグ
|
オルグとは一般に「集団の組織化と指導を任務とするもの」をいうが、日新労組では本部(または分会)の運動方針や見解について、徹底を図る会議のことをオルグとしている。本部オルグは分会に対し通常年2回、組合大会の前に行っているが、分会によっては独自に分会オルグを実施しているところもある。また、オルグを行う人をオルガナイザー(organizer)ということもある。 |
経営協議会
ケイエイキョウギカイ
|
経協(ケイキョウ)ともいう。労働協約において「社業の円滑な運営と経営の合理化を図るため」に会社と日新労組が設置することとされている。経営協議会では従業員の賃金ほか労働条件に関わる事項、会社の職制、機構に関する事項などについて協議することとしている。経営協議会委員は、組合側は本部執行委員全員、会社側は社長以下8名が委員となっている。 |
職場会
ショクバカイ
|
組合のすべての活動や取り組みは、職場からの意見や声に基づいて行っており、組合活動の原点となるもの。組合員の納得と合意のもと、取り組みを進める「民主的な労働組合」を目指している。 |
専従
センジュウ
|
組合業務に専門に従事している者のこと。専従役員になると、会社は休職扱いとなり、給料ほか通勤費や社会保険料の会社負担分などは会社から支給されず、組合費より支給をされることになる。 |
小委員会
ショウイインカイ
|
経営協議会(経協)に次ぐ、会社との協議機関。協議する議題に応じて、経協・小委員会・事務折衝を開催している。組合側出席者は本部四役(委員長、副委員長、書記長、副書記長)および常任執行委員、会社側は人事担当役員以下、人事企画部長、人事企画課長となっている。 |
事務折衝
ジムセッショウ
|
会社との協議機関としては最も低いレベルとなっており、日常の協議などはほとんど事務折衝(事折:ジセツともいう)で行っている。会社側は通常、人事企画課長が対応し、組合側は書記長または副書記長(副委員長)の専従役員が交渉にあたっている。 |
地方運営会
チホウウンエイカイ
|
経営協議会が日新労組・会社(人事)との協議であるのに対し、地方運営会は各分会で本部長または部長などの部店経営と協議を行っている。また、各職場で発生した問題については基本的にまず分会と部店経営で協議を行うこととなっている。 |
本部闘争委員会
ホンブトウソウイインカイ
|
日新労組の争議や要求の貫徹のために、組合大会の決議により、本部闘争委員会は設置される。通常は、「賃金闘争の業務を執行し、その指導にあたること」を主な課題とし、本部闘争委員会の構成員は本部執行委員があたっている。 |
拡闘
カクトウ
|
拡大闘争委員会の略。拡闘は本部闘争委員会に各分会委員長が参加し構成する。 |
分代
ブンダイ
|
分会代表者会議の略。本部執行委員と各分会の代表者(=委員長)を交え、組合の方針などについて論議し、意思一致を図る会議またはそのメンバーのこと。例年では、春闘の組合要求を確立する前に開催され、基本的な方針について決定している。また、その他に従業員の雇用や処遇に大きな影響が及ぶような事態が生じた場合、緊急に召集されることもあり、本部と分会・職場との間で、情報の橋渡し役の立場も担う。 |